人間の体は頭、胴(胸+腹)、四肢で構成されています。
胴体は前面の内側に生命を維持するための重要な内臓が入っており、背面の脊柱は姿勢を保持する最も大切な心棒になっています。
精神的表現でも「背筋が一本通っている」とか「あの人は心棒が通っている」などといいます。脊柱は七個の頸椎(けいつい)、十二個の胸椎、五個の腰椎、五個が合体した仙骨、数個の尾骨で構成されます。第一頸椎(環椎)(かんつい)は俗に「ぼんのくぼ(盆の窪)」とも呼ばれ、頭骨に入り込んでいます。頭蓋底と、油膜性連結(骨同士の摩擦を防ぐための滑らかな分泌液をもった粘膜性の関節の一種)でつながり、頭の専心をささえる支点で、後頭筋群によって頭と体のバランスを保ち、頭の屈曲、伸展の役割をしています。
第二頸椎は別称軸椎(じくつい)とも呼ばれ、第一頸椎の椎孔(ついこう)に入る突起をもっていて、頭を回転させるとき、軸受けの役目をします。外から手でふれることのできる頸椎は、この二番目から下のものです。最も下にある第七頚椎は首の背面中央で、左右の肩につながる鎖骨と交叉する位置にあります。表面に突出しているので隆椎とも呼ばれ、自分の手で最も確かめやすい位置です。脊柱のつくるS字形のカーブは頸椎は前方に、胸椎は後方に、腰椎は前方に突き出し、上半身の頭と胸の重さを垂直にささえる柱の役目と、同時に立位のときに地面から足が受ける衝撃を和らげるクッションの役割をしています。そしてさらに脊柱の機能を補強するために、胴体の前面(腹側)および後面(背側) の筋肉群の働きもそれを助けています。骨盤は仙骨(五個の仙椎が一つに合体) と両側の腸骨が主体となってつくられた大きなブロックの総称で、上体と下肢をつなぐ位置にあります。
姿勢を保つために、形の上でも、機能的にも極めて大切なところです。脊柱の仙骨部分が両側の腸骨の間を縦に貫く形で交叉する、つまり十字路をつくるので、ドイツ語ではこの「仙骨」を「クロイツパインKreuzbein」と呼びます。脊柱全体の形と機能が全身に与える効果は、バネのような弾力性と体の重力に耐えるための強靭性です。人間が垂直に直立できるためには、地面に対する骨盤の傾斜角度が三〇度であることが適正だとされています。角度がそれ以上大きくなると上体は前に傾いてしまいます。因みに「腰」という文字は「月」(体の意)に「要」(かなめ)がついたものです。どっしり落ちついた人のことを「腰のすわった人」といいますし、東洋の呼吸法でいう「臍下丹田」(せいかたんでん)も骨盤底の内腔を指したものと考えられます。まさに人体のかなめにふさわしいところが骨盤です。姿勢の種類は人間のすべての行動から見ると無数にあるともいえますが、静止の状態では立位、坐位、臥位の三つになります。坐位には腰かけるときの椅坐位とすわるときの坐位がありますし、臥位にも仰臥位(仰向け)と伏臥位(うつ伏せ)、側臥位(横向き)があります。 次回は、立位、坐位、仰臥位を中心にお話します。できれば、「エクササイズ」まで述べます。 |
|
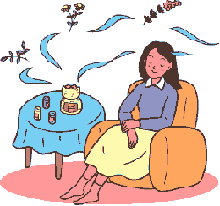
o○o ○。 o .・ 。 ・o ○ . o
o。心と身体の癒しに役立てます♪ o ・ .○ 。● 。o ○ ● ○o。o ○。o ○ |