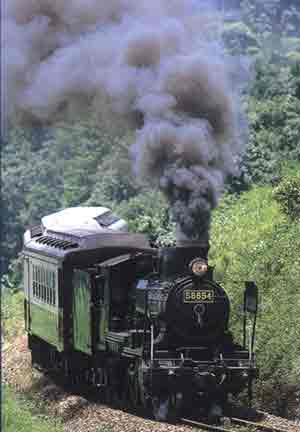元気のでる館 > 各地をご案内 > 熊本城
|

(水前寺公園)

(天守内部)
|
|

(路面電車) |

(熊本城) |
|
|
「JR鹿児島本線、豊肥本線熊本駅」 熊本県 熊本城
戦国時代、九州豪族菊池氏の一族、出田秀信が隈本の地に千葉城を築いた。現在の熊本城本丸のすぐ東の台地である。加藤清正の熊本城では城 郭 内となった。この台地は茶臼山と呼ばれ、明応五年(一四九六)になつて出田氏に替って鹿子木氏が入って隈本城と称した。は豊後の大友氏に属したが、その死後、鹿子木氏は菊池氏と結んだ
ので天文十九年(一五五〇)大友宗麟の攻撃を受け、隈本城には城親冬が入った。天正十五 年(一五 八七)豊臣秀吉の九州討伐ののち佐々戌政が肥後四十九万石で隈本城に入った。成政は治政を誤り失脚すると替って加藤清正が肥後半国二十五万石
を与えられ隈本城に入った。天正十六年のことである。隈本城に入った清正は、それまでの戦国の城を二十五万石の太守の居城 として改築をはじめたが、小田原の役、文禄、慶長の朝鮮出兵と居城を留守にすることが多く、築城工事の進展はおそかった。慶長三年(一五九八)豊臣秀吉が亡くなり、慶長五年、関ケ原の戦いが起こると清正は徳川家康に加勢し、戦後、肥後一国五十三万石の大守となった。ここで清正は慶長六年から新しい
構想で築城工事を開始した。七年の歳月をかけて慶長十二年にほぼ城を完成した。城の広さ約九八万平方メートル、本丸には大小、宇土の三つの天守、櫓の総数四十九基、櫓門十八、城門二十九をもつ五十二万石の太守にふさわしい巨城、名城であった。とくに石垣は清正の家中に石積みの巧者がいて、頑強な構造のうえに流麗な曲線を見せる特有の石塁を出現した。しかし加藤氏は清正の子忠広のと
き、寛永九年(一六三二)不都合があり改易となった。豊臣恩顧の大名をできる限り改易、除封する政策だったのである。替って熊本には細川忠利が豊前小倉から五十四万石で入封した。以降細川氏は世襲して明治に至った。明治四年(一人七一)になって城跡には熊本鎮台が置かれ、城地構築物、建物は保たれたが、明治十年の西南戦争が起こると鎮台は西郷軍の攻撃を受けた。激戦であったが落城しなかった。このとき天守が焼失してしまった。 |
|
|
熊本城には城内に約百二十の井戸があった。
現在も十七カ所が残るが、城内の井戸のいくつかは抜け穴に通じていたという。熊本城には抜け穴伝説も多い。城には城内から城外に通じる間道を 必ず造るのが城造りの定石であった。トンネルの場合は保持が難しいが、隠された道なら戦いに当って必ず役に立った。熊本城内に「首掛け石」と
いうコの字形の石が残っている。熊本城築城のとき横手の五郎という怪力の持ち主が首にかけ運んだという。五郎は天草の一撥のとき清正に殺され た本山弾正の子で仇を討つため築城工事の人夫になったが、素姓が分かり、井戸に入れられ小石で埋められて殺されたという。熊本城は西南戦争のとき西郷軍に囲まれときの司令官は谷干城だったが、城内と政府軍の連絡に使った谷計助という下士官は間道を使った。この戦いの最中に天守閣が炎上した。城内の失火とも西郷軍の密偵の放火ともいわれ、原因は謎のまま。 |
|
|
|
|
|
|
|
|