| 湯抱温泉と大田市の彼岸市 湯抱温泉は大田市の彼岸市(春夏の彼岸の日に行われる)の時にあわせて利用すると便利。 元気のでる館 > 各地をご案内 > 島根県 万葉の旅へ 人麿の謎を秘め万葉のロマンを 関の五本松、安来節、 メノウの里で玉の肌を、玉造温泉 島根県大社町 祝世界遺産石見銀山 島根県津和野町 |
 |
|
| 湯抱温泉と大田市の彼岸市 湯抱温泉は大田市の彼岸市(春夏の彼岸の日に行われる)の時にあわせて利用すると便利。 元気のでる館 > 各地をご案内 > 島根県 万葉の旅へ 人麿の謎を秘め万葉のロマンを 関の五本松、安来節、 メノウの里で玉の肌を、玉造温泉 島根県大社町 祝世界遺産石見銀山 島根県津和野町 |
 |
|
目的の湯抱温泉は375号線沿 いに斎藤茂吉鴨山記念館(万葉の旅へ、人麿の謎を秘め万葉のロマンを)があり、ちょっと入った所に駐車場もあります。 車を降りて「日の出旅館」をたずね、不在・「中村旅館」でも不在。旅館は四軒ほど、375号線を戻り、左側にある「湯抱荘・外来入浴:大人500円 駐車場あり」に入ることに(大田市方面からは、右折後橋を渡る)。「二階の奥です」「矢印の表示にそってお願いします」行くと二 階の突き当たりに男湯と女湯があり、中浴場といった大きさです。他の客はなし。  お湯は茶褐色、鉄分が多く匂いはなし。39度くらいのぬるめのお湯で底は当然見えません。貸し切り状態の湯船の中でのんびりと、食塩泉だそうです。ぬるいのに汗がじわじわと出ます。
洗い場は5つほどカランが並びシャワーは一箇所だけ。レモン石鹸があるのがなんともいえず・・・。茶褐色のお湯からあがりましたが、いつまでも汗が止まりません。お湯はぬるかったのに後々までぽかぽかしています。茂吉は昭和12年1月7日、ここ粕淵村湯抱の苦木虎雄氏の手紙により、粕淵の地から3キロ離れた湯抱の奥に鴨山という名の山があることを知ります。 お湯は茶褐色、鉄分が多く匂いはなし。39度くらいのぬるめのお湯で底は当然見えません。貸し切り状態の湯船の中でのんびりと、食塩泉だそうです。ぬるいのに汗がじわじわと出ます。
洗い場は5つほどカランが並びシャワーは一箇所だけ。レモン石鹸があるのがなんともいえず・・・。茶褐色のお湯からあがりましたが、いつまでも汗が止まりません。お湯はぬるかったのに後々までぽかぽかしています。茂吉は昭和12年1月7日、ここ粕淵村湯抱の苦木虎雄氏の手紙により、粕淵の地から3キロ離れた湯抱の奥に鴨山という名の山があることを知ります。「斎藤茂吉(1882-1953)鴨山記念館」 万葉の歌聖柿本人麿は、持統・文武朝に宮廷歌人として華々しい存在から、その秀でた才能ゆえにか、何故か晩年国司として石見の国 (現在の島根県西部)に赴任したと言われています。当時、石見の国庁は現在の浜田市にあり、山陰本線 の下府駅(しもこう)のすぐ東に伊甘(いかん)神社という社があります。その境内の椋木の陰に、国府あとの石碑が建っています。 人麿は任地石見でそのままその生涯を終えたのでしょうか。 この歌の鴨山即ち人麿の終焉(708-715)の地は一体どこかと斎藤茂吉はこの「幻の山」を捜し求め て石見の山野を何度も実地踏査しました。そして、茂吉は昭和28年2月25日、数多くの業績を残し、惜しまれつつその生涯を終えました。湯抱で茂吉が何度も旅装をといた青山旅館には茂吉の泊まった部屋が今もそのまま残されています。今尚生き続ける人麿の心をそして茂吉を偲ぶため、この湯抱を訪れ茂吉の泊まった部屋を指定して泊まる遠来の客もあるといいます。柿本朝臣人麿の死りし時、妻依羅娘子(よさみのをとめ)の作る歌二首 |
|||
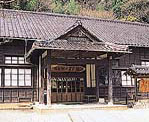 【石見銀山】 世界遺産 島根県・大田市石見銀山 【石見銀山】 世界遺産 島根県・大田市石見銀山家並みの中に、代官所の役人であった河島家、御用商人の熊谷家、両替商の寺脇家、芝居小屋の有馬家(今は和菓子屋有馬光栄堂)、郷宿の青山家、その他数軒の建物が当時の様子を残して並んでいる。 武家屋敷と町家では構造が違うのが、これだけ並んでいるとよく分かる。 石見銀山の発見は、博多商人の神谷寿偵が日本海を船で航行中、月明かりに光る山を見て、すぐに鉱山の開発に着手し、大陸からの技術者を迎 え「灰吹法」を導入(1533年) 石見銀山はもともと大内氏の所轄地だったが1557年毛利氏が奪取した。 岩室山羅漢寺 銀山川に架かる優美な反椅のむこうの石窟に、寺の住職月海上人が発願した五百羅漢坐像がある。 中央に釈迦三尊、右窟に木蓮尊者を中心に250体、左窟に阿難尊者を中心に250体、それぞれの表情で坐している。これらは亡くなった鉱夫の霊 を弔って造られたもの。 石窟の左手にある宝筐印塔は御三卿田安家が寄進。かって銀を掘り進んでいった道を歩いてみよう。坑道は116 m通り地上に出るのだが、内部の壁に「石見銀山絵巻」が展示してあり、当時の坑内の様子がよく分かる。 芋殿様 井戸平左衛門正明(60歳)が19代代官として1731年9月初めに大森へと江戸を旅立ちました。「大岡裁き」で有名な大岡忠相が勘定奉行所の役人であった平左衛門を抜擢します。9月末に石見の国へ到着した平左衛門は、その名の通り田の稲も立ち枯れたままの岩ばかり目につく「いわみの国」の貧しさに驚きます。石見の国は、このところ凶作続きでした。当時の運上銀は百貫程度に減っています。1733年は大飢饉の年で、三十万人が食べ物がなく餓死したといわれます。着任早々のウンカの大発生による深刻な凶作です。後に「江戸時代の三大飢饉」として知られる「享保の大飢饉」です。自分のお金や寄付を募り施粥に尽す傍ら、1733年4月大森の栄泉寺で養父の法要を営んだ折、井戸正明は薩摩の修行僧泰永から、から芋の存在を知り、救荒作物(栄養豊かで、年貢からもはずされます)としてサツマイモで飢饉に対処できるように、当時国内鎖国主義だった薩摩から種芋を入手した。しかし栽培方法が分からず、植え付け時期が遅かったこともあり次々失敗。ただ一人邇摩郡福光村(現・大田市温泉津町福光)松浦屋与兵衛という老百姓が種芋の収穫に成功しており、越冬技術も開発され、寒い地方におけるサツマイモ栽培が可能となって、石見を中心に近隣へ普及することとなった。 芋博士として知られる江戸の青木昆陽が関東地方に芋をひろめるよりも二年も前の事です。 享保の大飢鮮の時、彼は農民の窮状を救うため、やむなく幕府の米蔵を開放し、米を毎日配り、種モミまで用意しました。以後多くの農民を飢餓から救います。井戸平左衛門正明はその後「芋代官様」、「芋殿様」として人々に敬慕されます。遺徳を後世に伝えるため当時の人々が芋塚と呼ばれる頌徳碑や供養塔を建立しています。現在その数は中国地方を中心に400を超える徳をたたえる碑があります。 略歴 寛文12年(1672年)に江戸に生まれ、元禄5年(1692年)に井戸平左衛門正和の養子となる。 元禄10年(1697年)に表大番、元禄15年(1702年)に御勘定に昇進。 享保16年(1731年)に第19代大森代官に着任(直後に備中倉敷代官の病死により倉敷代官を兼務)。 享保18年(1733年)5月26日に備中倉敷代官所の笠岡出張代官所で死去(死因は救荒対策からきた過労による) 江戸のときからの友人、久世代官(岡山県津山市)窪島作右衛門(倉敷代官を交代で務める)の二男正武を養子に迎えています。1733年4月に遺言状を正武に書いたものが大田市大森町の井戸正明を祀る井戸神社にあります。その一節を「この度の病気は重く、回復は難しいと思うので、一筆書き遺しておく・・・」長文の遺言状は武士の心得を丁寧に教えさとします。1733年4月18日ごろ、容体が悪くなり、多くの医師が診ています。地元笠岡・福山・岡山・三次など計13名。遠く石見の医師の記録から、現在の心臓性ぜんそくと、肝硬変と診立てます。墓所は威徳寺(岡山県笠岡市)。 銀山街道 大森から尾道に至る130kmの道を銀山街道という。1箱10貫目(40kg)入りの銀2箱を載せた馬200頭以上、人足はその倍以上、年に1度旧暦11月中旬、菰に包んだ銀箱に葵の紋の幟を立てて3泊4日で尾道まで運んだという。尾道からは船で大坂へ運び、大坂で貨幣に鋳造された。 |