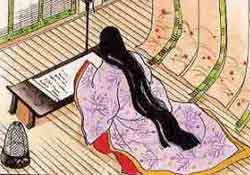
昭和の時代へ
昭和中期、林芙美子(1903-51山口県生まれ)
と壷井栄(1900-67香川県生まれ)ふたりのがペンを握った上林温泉。
ご当地民謡長野県木曽節、小諸馬子唄
| 『放浪記』『二十四の瞳』の生まれた 長野県 上林温泉 長野県は「十州に境連ヌル国」といわれ、現在でも愛知県・岐阜県・富山県・新潟県・群馬県・埼玉県・山梨県・静岡県の八県と県境を接している。地図の上では日本の中心といえ、首都がココでも不思議はないが山や川の有名な名がみられるところをみると・・・(御嶽・乗鞍・駒ケ岳・浅間・槍ヶ岳・八ヶ岳・犀川・千曲川・木曽川・天竜川) |
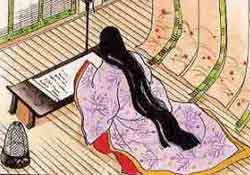 |
ふたりの女流作家の魅惑的な隠れ家を訪ね、 昭和の時代へ 昭和中期、林芙美子(1903-51山口県生まれ) と壷井栄(1900-67香川県生まれ)ふたりのがペンを握った上林温泉。 ご当地民謡長野県木曽節、小諸馬子唄 |
元気のでる館 > 各地をご案内 > 長野県
|
明治九年、松本にあった筑摩県庁が焼失したのを契機に、長野県に筑摩県が合併された。当時、筑摩県は南信濃の筑摩・安雫諏訪・伊那四郡と飛騨国を領域としていたが、南信四郡は長野に県庁を置く長野県に、また飛騨国は岐阜県に編入された。その結果、信濃国は行政区画の長野県と一致することになった。ところが、旧筑摩県に属する南信(中南信ともいう)の人びとは、県庁があまりに北に偏在していることを怒り、事あるごとに松本に県庁を移せという移行論を唱え、それが不可能ならば県を二分せよという分県論を主張してきた。このような地域間対立は、他県にもみられるが、長野県ほど強いところはあるまい。このような意識が強いために、長野県では「信州人」という表現が一般化している。国立の信州大学は、本部は松本にあって、長野大学と呼称していないのも、地域間対立の産物であった。南北一一二キロにもおよぶ長野県には、中央アルプス(木曽山脈)をはじめ、いくつかの山脈があり、それらが県土を分断している。そのため生活圏は八つの盆地ごとに異なっている。信州人はよく「信濃国は十州に境連ぬる国にして、そびゆる山はいや高く、流れる川のいや遠し」と「信濃の国」の歌をうたう。この唱歌は明治三十三年長野県師範学校教諭浅井きよしの作詞、同校教諭北村季晴の作曲によるものだが、師範学校の卒業生が子供たちに教えたことから全県的にうたわれるようになった。昭和四十二年この 「信濃の国」は長野県歌に選定されたが、八十年も前につくられた唱歌が県歌になっているのは、他に例をみない。これは「信濃の国」 の歌が、県民歌として長い間うたわれてきたからであった。そして、この「信濃の国」を斉唱すると、不思議と一体感が生れてぐる。〝合衆国″である信州でほ、観念的にだけでも、ひとつになろうという考えから、この歌がよくうたわれているのであろう。 |