生きるとはエネルギーを使いつづけることです。
私たちに必要なエネルギーは熱量として計算されます。
私たちは生きているかぎり体温生産を続けなければなりません。
睡眠中も活動中も身体は生命を維持するためにエネルギーを消費しています。このように、人間が生命を維持するために基本的に必要なエネルギー代謝を「基礎代謝」と言います。
この基礎代謝は、人間の一生では中学生〜高校生(人体1平方mあたり50キロカロリ−)くらいのときに最大となり、四十代(人体1平方mあたり30キロカロリ−)になると急速に低下していきます。
カロリ−はエネルギーの単位です。
1gの水を14.5度から15.5度上げるのに必要な熱量のこと。
安静時に必要なエネルギー量(基礎代謝量)は成人では1300から1600キロカロリ−となります。安静にして横になっているとき、体内のどこでエネルギーが消費されているのか、体温の生産はどこが活発になるのかを考えてみましょう。最も大量に消費するのが筋肉(呼吸筋)で、全体の六〜七〇パーセントにもなり、残りを心臓などの臓器がそのエネルギー消費をしています。
私たちは安静時にも、約1500キログラムの水を一度上げるのに必要な熱量を使っているのです。 このエネルギーはどこから?
これは、ご存知の食物から取り入れられるエネルギー基質、すなわち糖質(炭水化物)、脂質(脂肪)、たんぱく質であり、これらは体の中の酸素と反応できる基質を持つ物質です。酸素と反応してできたエネルギー(ここは次号で)は、仕事エネルギーのほかに熱エネルギーにもなり、その使用エネルギーを超えたエネルギーは身体の中に蓄えられます。
食物から取り入れられるエネルギー熱量は、糖質(炭水化物)は1gあたり約4キロカロリ−、脂質(脂肪)は1gあたり約9キロカロリ−、たんぱく質は約1gあたり4キロカロリ−であり、基礎代謝量は成人では1300から1600キロカロリ−、普通に生活している場合には、成人では2000キロカロリ−必要となります。
実際には、エネルギ−需要の63%が糖質、25%が脂質、残りの12%たんぱく質でとるのが良いとされています。
逆算しますと、エネルギ−需要は320gが糖質、55gが脂質、60gがたんぱく質でとるのが良いとなります。
肥満で摂取カロリ−を落とす場合、糖質は10%まで落とせますがそれ以下に落とすと障害をおこします。(他の2栄養素は次号にて)脳神経細胞の活動エネルギ−はすべて糖質からとります。
酸素はなぜ必要?
簡単には栄養素が燃焼するために・・・。
食物のもつエネルギーの95%は、体内でそれ自身のもつエネルギー(自由エネルギー)となりますが、そのままの形ではエネルギーとして使うことはできずいったん別の形で蓄えられます。
この蓄えられたエネルギーの55%は身体の体温を保つためのエネルギ−となり、残り45%が活動エネルギーということに・・・・。 |
|
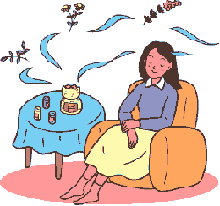
o○ o ○。 o .・ 。 ・o ○ . o
o。心と身体の癒しに役立てます♪ o ・ .○ 。● 。o ○ ● ○o。o ○。o ○ |