| 成功する農業大国、食料輸入最大国の汚名返上 | |
| 元気のでる館 > 健康癒し能力開発グッズ > 近代日本へ砂鉄のみち | |
|
出雲というのは、神話と現実が、歴とした現実の中でいりまじっている土地で、洞穴をくぐると不意に神話の風景がひらけたりして、かんが狂ってしまう。たとえば鳥上山というのは、スサノオノミコトがその山で八岐大蛇を退治して天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を獲た所として知られる。『古事記』にいう「肥河上(ひのかわかみ)なる鳥髪の地(とりかみところ)」なのである。神話の中で、スサノオに退治られる鳥上山の八岐大蛇というのは、鳥上山にいた舌代の砂鉄業者であるという。出雲ではたれもがそのように言うし、もっともな解釈かと思える。古代には砂鉄を採集し山中でこれを鉄にする専門家が群れをなして中国山脈を移動していた、というのが1この解釈の前提になっている。想像するに一団は百人以上だったであろう。 |
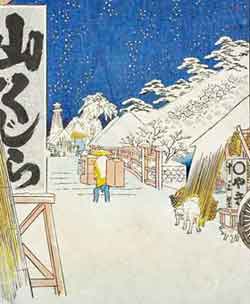 |