愛知県、三河湾国定公園観光の中心渥美(あつみ)湾北岸にある蒲郡市 「伊良湖」は、愛知県東部、三河湾国定公園「渥美半島」の先端に位置し、年平均気温16℃というその温暖な気候風土により、「リゾートエリア」として知られています。ご当地民謡愛知県岡崎五万石 「伊良湖」は、愛知県東部、三河湾国定公園「渥美半島」の先端に位置し、年平均気温16℃というその温暖な気候風土により、「リゾートエリア」として知られています。ご当地民謡愛知県岡崎五万石⇔【椰子の実詩碑】 もしかしたら、あなたも、流れ着いたやしの実を見つけることができるかも……。 蒲郡(がまごほり)を愛した文人たち谷崎潤一郎・川端康成・菊池寛・山本有三・高濱虚子 「細雪」「無事の人」「右門捕物帖」「旗本退屈男」の生まれた地に歴史のロマンを |
| 元気のでる館 > 各地をご案内 > 愛知県 谷崎潤一郎ほど蒲郡の佳さを喧伝してくれた作家はいません。かれの作品のなかで蒲郡が書かれている「細雪」は八年がかりで完結をみた大作です。執筆中に太平洋戦争という時を経験した谷崎は、戦争が終末をむかえたとき、蒲郡の美しい海を夢想して、戦後すぐに書きはじめた下巻のはじめに、幸せのうすい主人公の雪子が蒲郡まで旅行し、そこでやすらぎを得る設定をもってきました。谷崎は戦時中について、「あの吹きまくる嵐のような時勢」といい、嵐のおわりを象徴するのは、日本広しといえども蒲郡でなくてはならなかったようです。谷崎の夫人、千代のことで絶交していた友人の佐藤春夫が吉野からやってきて、谷崎のいる旅館(おそらく常磐館)にニ日間、泊まった。前年に和解が成っていたニ人は蒲郡の宿でどんな話をしたのでしょうか?。谷崎が石川千代と結婚するとき媒酌をしたのが志賀直哉です。志賀も蒲郡を気にいった人です。というより蒲郡ホテルが気にいったのですが・・・ 蒲郡ホテルは旅館の常磐館とは姉妹館になり、常磐館の敷地内に昭和九年に建てられました。 昭和十六年一月二十七日からニ月一日までの滞在中にあの有名な『内村鑑三先生の憶い出」を書きました。 蒲郡の常磐館のすばらしさを最初に日本中に知らしめたのは菊池寛です。 かれは大正十一年の三月から「大阪毎日新聞」に連載した小説「火華」の冒頭で蒲郡を褒めにほめました。 その「火華」に旅情を誘われたかのように蒲郡の地を踏んだ青年作家が川端康成です。かれは作品を菊池寛に認められ文壇に登場し、大正十四年に常磐館を背景につかった短編「驢馬に乗る妻」を発表。この大正十四年に生まれたのが三島由紀夫です。三島は小説「宴のあと」で蒲郡を主人公の新婚旅行先にえらびました。 逆に夫婦関係の破局の地に蒲郡がえらばれた作品が立原白秋の「船の旅」です。 |
| 山本有三は昭和四年に病をえたが翌年退院し、静養地として蒲郡をえらびました。 そして蒲郡の海を小説「無事の人」(昭和二十四年)に書きました。 蒲郡で療養生活をおくった作家に、「右門捕物帖」「旗本退屈男」の佐々木味津三がいます。 佐々木味津三の友人が尾崎士郎です。 尾崎士郎は蒲郡市の西隣の地に生まれ現在の岡崎高校を卒業し早稲田大学へはいりました。 代表作『人生劇場』に蒲郡はたんなる乗り換え駅の名としてしか扱われていません。 蒲郡を訪れたのは小説家ばかりでわなく、俳人や歌人もいます。 俳人といえは高濱虚子です。 昭和十四年に常磐館にて 春の波 小さき石に ちょと踊る という句を詠んだ。二月十二日のことです。 歌人は佐佐木信綱・治網父子で、蒲郡をうたった歌が四首あります。 蒲郡の夏を彩る一大フェスティバル(蒲郡まつり)。 中央通りでのパレードや蒲郡おどりなど、盛りだくさんのイベントで賑わいます。 フィナーレを鮮やかに飾るのは、三河湾の夜空を盛大に照らす納涼花火大会です。正三尺玉花火は、直径650mの大輪の花を咲かせます。この花火をひと目見ようと、各地から大勢の人々が集まります。花火の名産地である三河ならではの技を生かした花火が繰り広げられ、夜の海岸をファンタジックに演出します。 |
伊良湖の地名は伊良湖崎近くで、東大寺の瓦を焼いた窯が発見される等、古くから歴史に登場。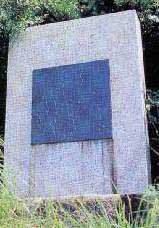 伊良湖には万葉の頃から岬の豪快な景色を愛でて、多くの文人墨客が、詩歌を残しています。 万葉集の柿本人麻呂の歌に 題詞 (幸于伊勢國時留京柿本朝臣人麻呂作歌) 潮騒に伊良虞の島辺漕ぐ舟に妹乗るらむか荒き島廻を 番号 01/0042 原文 潮左為二 五十等兒乃嶋邊 榜船荷 妹乗良六鹿 荒嶋廻乎 仮名 しほさゐに,いらごのしまへ,こぐふねに,いものるらむか,あらきしまみを 万葉歌碑 岬の先端、灯台背後の古山の斜面に、天武朝の皇族であった麻績王の歌碑があります。麻績王は遠く都を追われ、伊良湖の浜に身を寄せていました。それを憐れむ里人の思いやりに応えた歌で、潮騒の浜にふさわしい万葉の名歌といわれています。 「うつせみの 命を惜しみ浪にぬれ 伊良虞の島の 玉藻刈り食す」 (この世の命が惜しさに私は波にぬれて、この伊良湖の島の海藻を刈って食べているのです。) 【芭蕉の句碑】 「鷹一つ見つけてうれし伊良湖崎」  伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部の入口近くに芭蕉の句碑があります。これは芭蕉が貞享四年(1687年)11月、保美の里に隠棲していた愛弟子の杜国を訪ね、伊良湖崎を清遊した時に詠んだ句です。 【椰子の実詩碑】 民俗学者・柳田国男が明治31年の夏、伊良湖に1カ月余り滞在した時拾った椰子の実の話を親友の島崎藤村に語った。それがもとになって椰子の実の叙情詩「名も知らぬ遠き島より流れよるやしの実ひとつ…」を書きました。 後に昭和11年、大中寅二作曲による、国民歌謡として全国に放送され、伊良湖崎の名を全国に知らしめました。 もしかしたら、あなたも、流れ着いたやしの実を見つけることができるかも……。 【弘法大師像】 金剛寺 住所/愛知県蒲郡市三谷町南山1−17 弘法山の山頂に立つ、高さ18.78mの弘法大師像は、子育て、子授かり、所願成就などのご利益があるとして知られ、ここから見る街の眺めは「蒲郡八景」の一つです。 |