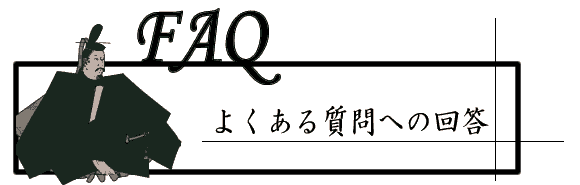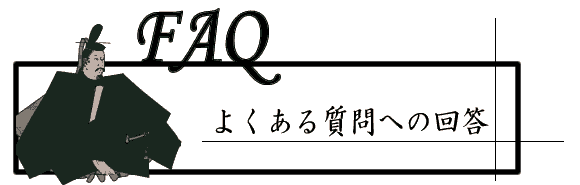| 質問 |
パワーストーン広島 > 各地をご案内お遍路 >よくある質問 |
| Q1、納経所の受け付け時間は? |
人間の持つ“自然治癒力”を高める
家庭用電気磁気治療器「バイオイーザーBR-701」
医療用具許可番号 34BZ5006 |
| お遍路四国巡礼ー簡単 Q&A |
回答 |

お遍路について |
各札所で納経を受け付けている時間は、午前7時〜午後5時までときまっている。ただし、山間部にある札所などでは、早めに受け付けを終えるところもある。また、日曜や祝日は参拝者も多く、混雑が予想されるので、余裕を持って参拝するようにしたい。
納札には何を書くの?
巡礼者本人の名前、年齢、住所、年月日(お参りした日)、願い事を書く。四国霊場では、1カ寺ごとに本堂と大師堂の2カ所の納札所におさめることになっている。
何色の納札を選べばいい?
納札には、白、赤、金など、さまざまな色がある。この色は、巡礼の回数によってきまっており、巡礼者はそれぞれに合ったものを使う。白は1〜4回、緑は5〜7回、赤は8〜24回、銀は25〜49回、金は50〜99回、100回以上は錦札を使うのが通例となっている。 |
| 質問 |
|
| Q2、意味がわからないのに、お経を読んでもいい? |
|
|
回答 |
 |
特に問題はない。意味を無理に理解するより、供養したいことや自分の願うことを、心を込めて読めばよい。 ただし、お経は仏教の世界に古くから伝わるありがたい教え。ふだんから勉強しておくことをおすすめしたい。経本を見れば、お経を覚えていなくても安心 |
| 質問 |
|
| Q3、お説教はいつでも聞けるもの? |
|
|
回答 |
| |
説教を聞くのはなかなか難しい。ただし、宿坊に泊まると、朝夕に住職がお説教の時間をとってくれる場合がある。また、個人の相談を受け付けている寺もあるので、どうしてもという場合は、寺に直接問い合わせてみるとよい。 |
| 質問 |
|
| Q4、宿坊に泊まりたいが、その利用方法は? |
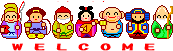 |
| |
回答 |
| |
予約方法は、普通の宿泊施設と同様、寺に予約の電話を入れる。札所によっては、一定の期間のみの営業だったり、団体利用客のみ利用可であったりするので、必ず事前に確認しておこう。宿坊では、それぞれの施設の規則に従えばいい。ただし、消灯は、宿坊に泊まるほとんどの人が翌日に備えて午後9時にしているところが多い。いっしょに宿泊している人に迷惑をかけないためにも、就寝は早めにしよう。宿坊に泊まるだいご味は、早朝や夕方に行われる勤行(ごんぎょう)。旅館やホテルでは味わえない経験だけに、参加してみるとよい。また、札所によっては、住職の法話を聞くこともできる。
宿坊以外に無料で泊めてくれる善根宿もある |
| 質問 |
|
| Q5、遍路道にはきめられたコースがあるの? |
|
|
回答 |
 |
 特にきめられたコースはありません。 特にきめられたコースはありません。
ただし、「へんろみち保存協会」が、文献や聞きとり調査をもとに選定した、古くから伝わる遍路道がある。これは昔から伝えられた行き方なので、新道や舗装された道を通らなかったり、わかりづらいことも多い。
しかし、保存協会が道の分岐点や角に、赤い文字の標識を設けてくれているので、これを目印に進むとよい。
旧遍路道には、へんろみち保存協会が立てた標識が随所に⇒ |
| 真言宗を信仰していなくても、八十八カ所を巡礼していいの? |
修行の旅なので、功徳を積んで苦悩から救われたい、あるいは霊場を巡ることで弘法大師の教えを学びたいと思う者であれば、ほかの宗教の信徒でも支障はない。一人一人がそれぞれの目的を持って遍路に臨めばよい。ただし、巡礼用品の輪袈裟はお釈迦様をあらわすものであるので、仏教信者以外は身につけないほうがよい。 |
| 適札は第一手札所から回らないといけないもの? |
第一番札所霊山寺から始めるのが一般的だが、特にきまりはない。交通の便のよい寺から始めてもよいし、自分の思い入れの強い寺から始めてもよい。第八十八番札所大窪寺から始めて、逆に回っていくことを 「逆打ち」といい、その道の険しさなどから、普通に回るより3回相当のご利益があるといわれている。 |
| 鐘は自由についてもいいの? |
鐘をつくことには、仏を呼び起こすという意味がある。何度もつくようなことは避けたい。 また、札所の近隣には民家も多い。近所迷惑にならないよう、あまり早い時間や深夜などは、つくのを避けるべきだろう。個人で巡拝している場合は、お鐘をつくのは心を込めて1回だけに。 |
| お賽銭の金額はどのくらい必要? |
お賽銭の金額は個人の自由。無理のない範囲にしたい。
あくまで志なので、金額は個人の自由。10〜50円を納める人が多いようです。 |