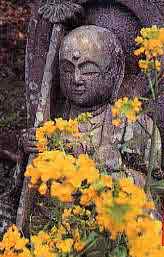 山頭火と井月 自然のエネルギーが持ち主に様々な作用を及ぼすというパワーストーンの波動やエネルギー、見えないけれども確実に身の回りに 存在するものを感じ取っていただき体や心の癒しに役立てます 昭和十一年六月 感激した山頭火 こおろぎに鳴かれてばかり 酔うてコオロギと寝ていたよ 元気のでる館 > 各地をご案内 > 中部地方 |
| 【井月】 本名は、一説によると井上克三といい、越後長岡藩の下級武士だったと伝えられている。 嘉永五年(一八五二)、信濃上伊那郡に飄然とやってきたが、出自はなお明らかでない。 上伊那郡では、一所不住の浮浪生活で、乞食井月と呼ばれていた。その俳句は俗風に染まぬ独自のものがあり、子規の前駆をなす近代性をおびている。  明治十九年の十二月には伊那で行き倒れとなり、そのまま死ねば迷惑とばかり、村人たちは戸板に乗せて厄介者を追い払った。次々にたらい回しにしたようだが、最後は上伊那郡美すず村の塩原梅関が引き受けて、明治二十年三月十日に死去。 明治十九年の十二月には伊那で行き倒れとなり、そのまま死ねば迷惑とばかり、村人たちは戸板に乗せて厄介者を追い払った。次々にたらい回しにしたようだが、最後は上伊那郡美すず村の塩原梅関が引き受けて、明治二十年三月十日に死去。梅関は彼のために小さな自然石の碑を建て、その正面に井月の句「降るとまで人には見せて花曇」を彫らせた。墓は梅開夫妻と同一のもので、戒名として塩翁斎柳家井月居士、俗名塩原清助と刻まれている。生前に身元引受人である梅関の弟として入籍していたからだという。こうした数奇な運命の俳人が遺した俳句を集めた『井月の句集』は大正十年に刊行され、それをさらに増補総合した『井月全集』が昭和五年に出版されていた。 山頭火はこれをしばしば読み、その生き方と俳句に傾倒していった。 今日ばかり花も時雨よ西行忌 井月 旅人の我も数なり花ざかり 井月 何処やらに鶴の声きく雷かな 同 落栗の座を定めるや窪溜り 同 山頭火(明治十五年〜昭和十五年)が生涯詠んだ句は、あわせて八万四千句にのぼるといわれている。 |
| 【山頭火】 山頭火の精神状態は、いつも周期的に起伏がひどい。 時には危険なところまで陥ることもあったが、そこから脱出する手段として旅があった。井月を発見して以後に、昭和九年三月二十一日、彼岸の中日の日記には「出立の因縁が熟し時節が到来した、私は出立しなければならない、いや、出立せせずにはゐられなくなつたのだ」と書く。久しぶりの大旅行。 飯田に住む「層雲」俳人の太田蛙堂宅に着くと寝こんでしまう。 ここまで来れば、伊那にある井月の墓は、そう遠方というところではない。 けれど身体は衰弱し、一週間後に退院すると、仕方なく飯田駅から飯田線で豊橋に出て、ほうほうのていで帰庵。日記には「木曾路で句作のいとぐちがやうやくほぐれかけたが、飯田で病んでいけなくなつた、そして帰来少しつゝほぐれる」と書く。山頭火の井月思慕は、ここでしぼまなかった。いや『井月全集』をさらに読みなおすし、昭和十三年三月五日には次のように書く。 「・・・私は遂に無能無才、身心共にやりきれなくなつた、どうでもかうでも旅にでも出て局面を打開しなければならない、行詰つた境地から真実は生れない、・・・窮余の一策として俳譜の一筋をたよりに俳諧乞食旅行に踏みさう!」 このとき、念頭には井月のことがあったはず。 翌日の日記には「今日は仏前に供へたうどんを頂戴したけれど、絶食四日で、さすがの私も少々ひよろひょろする、独坐にたへかね横臥して読書思索、万葉集を味ひ、井月句集を読む、おお井月よ」と印象的に書いている。 井月墓参はなかなか機縁が熟さない。 およそ一年後の昭和十四年三月三十一日に、ようやく出発することになった。 それも七年前は雪の失敗があるから、旅を急がない。 名古屋からは知多半島、渥美半島と回り道をした。 渥美町福町の潮音寺には芭蕉の弟子杜国の塞がある。  芭蕉の句碑もあったから、これを見学。 芭蕉の句碑もあったから、これを見学。鷹ひとつみつけてうれしいらご崎 芭蕉 はるばるたづね来て岩鼻一人 山頭火 山頭火は四月二十二日に奥三河の鳳来寺にも参拝。 その後は浜松に出て、そこより天竜川をさかのぼり、伊那に向かった。 そして五月三日に伊那に着き、地元の「層雲」俳人に案内してもらい井月墓参。 その『旅日記』には、井月の墓やその周辺の様子を詳しく書いている。 山頚火にしてはめずらしい書きぶりだった。 井月墓前での山頭火の即吟は次の四句 お墓したしくお酒をそゝぐ お墓撫でさすりつ、はるばるまゐりました 駒ヶ根をまへにいつもひとりでしたね 供えるものとては、野の木瓜の二枝三枝 ついに墓参を果たした。井月の存在を知ってより、七年近くも経っていた。以来、念願だったことである。それにしても、この執拗さは何だろう。彼は自らの性格について、二十八年前の明治四十四年にすでに書いている。何ごとも一度でよく二度はかかわりたくないが、気に入って二度となるとき、それは千万度繰り返すものであり、終生離れ得ないものだという。山頭火の放浪性について、言い得て妙な自己弁明となつている。それは我がままな頑なさとも映るが、山頭火自身それを命がけで貫こうとしたところに大いなる衿持があった。 |